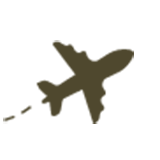フィリピンへの旅行や長期滞在、ビジネスを検討していると、「現地の消費税ってどうなっているの?」と気になる方も多いはずです。
この記事では、フィリピンの消費税(VAT)の基本的な仕組みから、税率は何%なのか、還付や免税制度はあるのか、さらに食品や日常サービスへの課税状況まで、わかりやすく解説しています。
東南アジア主要国との比較も交えながら、旅行者・滞在者・起業希望者それぞれに役立つ情報をお届けします。
- フィリピンの消費税(VAT)の基本的な仕組み
- 食品やレストランにおける課税の実態
- 還付や免税制度の有無と注意点
- アジア諸国との税制度の違いと比較ポイント
フィリピンの消費税 基礎知識

フィリピンの消費税は何%なのか?
フィリピンの消費税は「VAT(付加価値税)」と呼ばれていて、税率は一律で12%です。
これは商品やサービスを購入する際に自動的に価格に含まれているもので、日本でいうところの消費税とよく似ています。
日本と違うのは、フィリピンでは「税込み価格」が最初から表示されている点です。
スーパーやレストランで見かける値札やメニューの価格は、すでにVATが含まれている金額なので、レジで突然高くなるということはありません。
また、VATは全国どこでも同じ税率で適用されているので、地域によって税金が変わるということもありません。
日用品から娯楽まで、ほとんどのサービスに12%が課税される仕組みです。
Value Added Tax の略。
商品やサービスが売られるたびに「付加された価値」に対して課税される税金。
一般的に一律の税率で、内税方式(表示価格に含まれてる)のことが多い。
消費税と免税制度について

フィリピンでは、日本のようにパスポートを提示して消費税が免除される「免税制度」は基本的にありません。
観光客であっても、通常の商品やサービスを購入する際には、現地の人と同じように12%のVATが自動的に価格に含まれています。
唯一の例外として、空港内の免税店(Duty-Free Shop)があります。
ここでは一部の商品が税金なしで販売されており、旅行者や帰国者などが対象になります。
とはいえ、市街地のショッピングモールやコンビニなどでは免税の対象にならないため、
「フィリピンでは基本的に免税はない」と覚えておくと安心です。
食品にかかる消費税
フィリピンでは、ほとんどの食品に対しても消費税(VAT)12%が課税されます。
スーパーでの買い物やコンビニなど、日常的に手にする加工食品・飲料・調味料なども基本的には課税対象です。
ただし、一部の生活必需品や生鮮食品(野菜・米など)には非課税の扱いがされていることもあります。
こういった商品は、レシートに「VAT Exempt」などと表示されることがあり、課税されていないことが確認できます。
とはいえ、全体的に見れば「食品=非課税」とは限らないので、購入の際に気になる場合はレシートをチェックしてみるのがおすすめです。
レストランと消費税の関係

フィリピンのレストランで食事をすると、基本的に表示されている価格にVAT(12%)がすでに含まれています。
つまり、メニューに書かれている金額は「税込み価格」であり、あとから税金が加算されることは基本的にありません。
ただし、お会計時にはレシートに「VAT額」が別途明記されているため、「税金がどれだけかかったのか」をしっかり確認することができます。
また、レストランによってはサービス料(通常5〜10%)が別で加算されることもあります。
VATとは別の項目になるため、「表示価格+サービス料」という形で合計金額が少し高くなるケースもあります。
外食する際は、「VAT込みだけど、サービス料は別」と覚えておくと、より安心して利用できますよ。
消費税は還付されるのか
フィリピンでは、日常生活で支払った消費税(VAT)が還付されることはほとんどありません。
旅行者や一般の買い物客が、購入時に支払った税金を後から取り戻すような仕組みはないんです。
ただし、ビジネス用途や輸出関連の事業者などに対しては、「VATクレジット」という形で税金の還付制度が一部あります。
とはいえ、これはあくまで企業向けで、旅行者や在住者が利用できるものではありません。
そのため、普段の買い物や外食で発生するVATは「戻ってこないもの」として考えておくと、トラブルになりにくいですよ。
東南アジアの主要国と比べたフィリピンの消費税

フィリピンの税金は本当に高いのか
フィリピンの消費税率は12%。
この数字だけを見ると、日本の10%よりやや高く、アジアの中でも比較的高水準に位置します。
ただし、税率の「高さ」だけではなく、それがどのような経済状況の中で運用されているかにも注目する必要があります。
フィリピンは、物価自体は日本より安いとされることが多いものの、平均所得もそれに応じて低めです。
そのため、同じ12%でも、家計に与えるインパクトは日本より大きく感じる人もいます。
さらに、フィリピンの消費税(VAT)は一律課税で、所得や生活レベルに関係なく全ての人が同じ税率を負担します。
とくに所得の少ない層にとっては、生活必需品にも課税されることが負担感につながりやすいのです。
こうした背景から、「税金が高い」というよりも、負担の重さが不均等に感じられるという声があがるのも納得できるところです。
税制度自体はシンプルでわかりやすい反面、社会的な公平性の面では見直しの余地があると感じる人も多いようです。
実はあるフィリピンのシニア割引
日本の場合でもありますが、それは店舗独自のサービスであることがほとんどで公のサービスとしての
シニア割引はほとどんどないかと思います。
フィリピンで病院、交通機関、レストラン、食品などが20%割引+VAT免除の精度があります。
最初はなぜIDを出してしるのかわからなかったのですが、国のルールとしてそういった制度があります。
日本人であってもリタイアメントビザなどを所有している居住者であれば
IDが発行されてレストランなどでは割引の対象になります。
タイ・インドネシアなど東南アジア主要国の消費税は?

フィリピンの消費税(VAT)は一律12%ですが、東南アジアの他の国々を見てみると、制度や税率にはさまざまな違いがあります。
タイ
タイのVATは7%と比較的低めです。
生活コストとのバランスを取るためにこの税率が維持されており、観光立国としての競争力にもつながっています。
インドネシア
インドネシアは2022年にVATを10%から11%に引き上げており、今後12%に上がる予定です。
経済成長と財政の健全化を意識した段階的な引き上げが行われています。
ベトナム
ベトナムではVATが導入されており、標準税率は10%です。
ただし、生活必需品や一部サービスには5%または非課税の対象もあります。
税率は日本や韓国に近い水準ですが、所得水準を考えると日常生活への影響は少なくありません。
シンガポール
シンガポールではGST(物品サービス税)が導入されており、2024年に8%から9%に引き上げられました。
医療や教育、住宅の販売などには非課税またはゼロ税率が適用されるなど、制度は先進国型で柔軟性のある設計となっています。
物価が高いため、税率は控えめでも消費者の負担は相応に大きいことがあります。
Goods and Services Tax の略。
VATと似ているけど、国によって細かい仕組みが異なる。
税率が複数に分かれていて、商品ごとに税率が変わるのが特徴。
マレーシア
マレーシアでは、2018年に「GST(6%)」が廃止され、現在はSST(販売税・サービス税)制度が導入されています。
この制度では、商品には5〜10%の販売税が、サービスには6%のサービス税がそれぞれ課せられるしくみになっており、VATのような一律課税とは異なります。
購入するモノや利用するサービスによって、課税の有無や税率が変わるのが特徴です。
Sales and Services Tax の略。
販売税(Sales Tax)とサービス税(Service Tax)を別々に課税する仕組み。
商品には販売税、サービスにはサービス税がかかる。
このように比べてみると、フィリピンの「一律12%」という制度は柔軟な調整は難しい反面、明快で理解しやすい制度ともいえます。
フィリピンと各国の消費税まとめ比較
これまで見てきたように、フィリピンの消費税(VAT)は一律12%で全国どこでも同じ税率が適用されるシンプルな仕組みが特徴です。
下記の表では、フィリピンと東南アジアの主要国、そして日本を含めた各国の消費税制度を比較しています。
東南アジア+日本の消費税比較表
| 国名 | 税制度 | 税率 | 主な特徴 |
|---|---|---|---|
| フィリピン | VAT | 12%(一律) | すべて内税、全国一律、課税範囲広い |
| タイ | VAT | 7% | 低率で観光業とのバランス重視 |
| インドネシア | VAT | 11%(将来12%) | 段階的に税率引き上げ中 |
| マレーシア | SST | 販売税5〜10% / サービス税6% | GST廃止後にSST導入、用途別に課税 |
| ベトナム | VAT | 5% / 10% | 一部非課税対象あり、標準税率は10% |
| シンガポール | GST | 9% | ゼロ税率・非課税対象あり、先進国型の柔軟な制度設計 |
| 日本 | 消費税(軽減税率あり) | 10% / 8% | 軽減税率あり、外税が一般的 |
フィリピンの消費税は、他国と比べて税率はやや高めですが、制度そのものは明快でわかりやすいという強みがあります。
一方で、日本やシンガポールのように軽減税率や非課税対象が設定されている国々では、所得層や生活スタイルに応じた柔軟な運用がされているのが特徴です。
どの制度が「優れている」というよりも、それぞれの国が抱える課題や社会背景に応じて設計されていると言えるでしょう。
フィリピンで生活する、あるいはビジネスや旅行を考えるうえで、こうした比較はきっと役に立つはずです。
フィリピンタガイタイで移住体験しませんか?
- 日本からわずか4時間半!
- 南国フィリピンの避暑地タガイタイ
- 美しい自然とフレンドリーな人々が魅力

\ まずはカバン一つで行ってみよう /